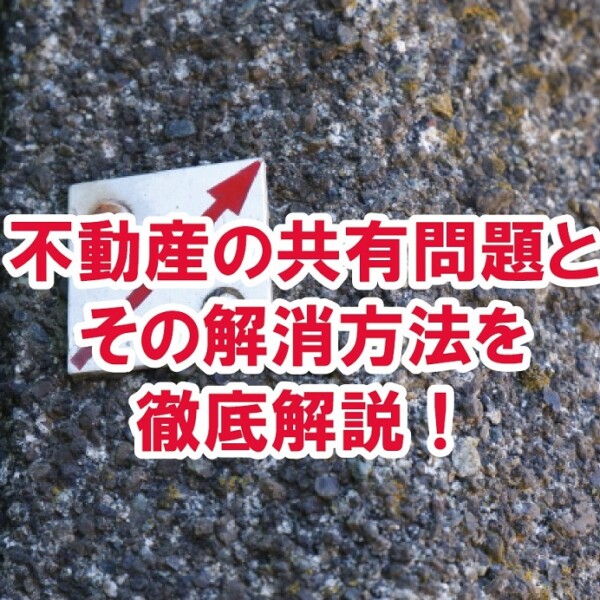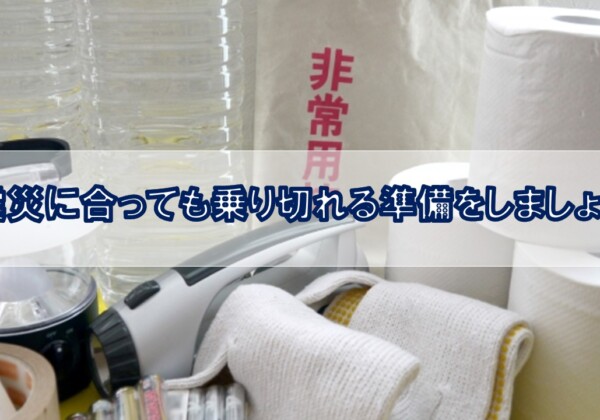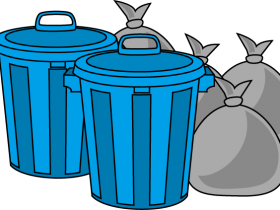■そもそも不動産の「共有」とは何か?!
不動産の「共有」とは、土地や建物を複数人で所有することを指します。日本の民法では、物理的に土地や建物を分割して所有するのではなく、「持分」という形で観念的に権利を分け合う方式が採用されています。たとえば、夫婦で購入した場合は「持分2分の1ずつ」、親族が一部出資した場合は「本人が10分の9、祖父が10分の1」といった形で所有権が設定されます。また、相続によって「母2分の1、姉4分の1、弟4分の1」など、複数人で共有状態になることも多く見られます。
■そもそも不動産共有の主な問題点とは?!
不動産の共有には以下のような問題点があります。1つ目は処分には全員の同意が必要という事です。共有不動産を売却したり担保に入れたりする場合、共有者全員の同意が必要です。たとえ持分がごくわずか(例:100分の1)でも、その人の同意がなければ処分できません。また、2つ目としては意見の不一致によるトラブルです。親族間であっても意見が一致しないケースは多く、共有状態が長期化するとトラブルの原因となります。3つ目は意思表示ができない共有者の存在が挙げられます。認知症や事故などで共有者の一人が意思表示できなくなると、手続きが進まなくなるリスクがあります。4つ目は税務リスクとなります。持分の決め方を誤ると「贈与税」が発生する場合があり、思わぬ税負担が生じることもあります。
■不動産の共有状態の解消方法について
不動産の共有問題を解消するためには、以下のような方法が考えられます。
(1)持分の売買
共有者のうち一人が他の共有者の持分を買い取ることで、単独所有にする方法です。持分だけの売買も可能ですが、当然ながら売買代金を支払う必要があり、資力が求められます。
(2)贈与・持分放棄
共有者が自分の持分を他の共有者に無償で譲渡する方法です。ただし、持分を無償で譲る場合には「贈与税」が課されることがあります。持分放棄の場合も、放棄された持分は他の共有者に自動的に移転し、やはり贈与税の課税対象となることがあるため注意が必要です。
(3)遺産分割
相続によって不動産が共有状態になっている場合、相続人全員で話し合い、各財産を分け合う「遺産分割協議」を行うことで、共有を解消できます。たとえば「不動産は母が取得し、株券は長男、現預金は次男が取得する」といった分け方が可能です。
(4)不動産の売却と現金分配
共有者全員で不動産を売却し、売却代金を持分に応じて分配する方法です。この場合、現物の共有状態を解消し、現金で分けることができるため、トラブルの回避につながります。
(5)遺言書の作成
将来的な共有状態を避けるために、遺言書を作成しておくことも有効です。遺言書で「この不動産は〇〇に相続させる」と明記しておけば、相続時に共有状態が発生しにくくなります。
■不動産の共有問題を避けるためのポイントについて
そもそも不動産の共有問題を回避するためには、「事前の話し合いと合意形成」が重要です。共有状態にする場合でも、将来のトラブルを避けるために事前にしっかりと話し合い、合意形成を図ることが大切です。また、「税務リスクの確認」も必要です。持分の設定や譲渡の際は、贈与税や譲渡所得税などの税務リスクを十分に確認しましょう。また、「専門家への相談窓口」を確保する。複雑な共有関係や相続、不動産取引に関しては、弁護士や税理士、不動産の専門家に相談することをおすすめします。
■不動産の共有問題とその解消方法のまとめ
不動産の共有は、相続や共同購入などで避けられない場合も多いですが、共有者全員の同意が必要なため、将来的なトラブルの火種となりやすいものです。共有状態を解消するためには、持分の売買や贈与、遺産分割、売却、遺言書の作成などさまざまな方法がありますが、いずれも税務リスクや手続きの煩雑さが伴います。長期的な視点で、できるだけシンプルな所有形態を目指し、早めに対策を講じることが重要です。誰もがトラブルを回避したいと思っていますが、相続等で大きな金額の不動産を目の当たりにした場合などに大きな問題となります。ぜひ、不動産購入前には、共有問題を考慮した半眼も重要です。今後の参考にお役立てください。
法人営業部 犬木 裕