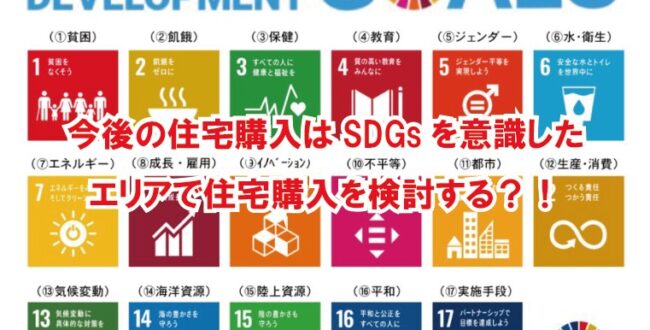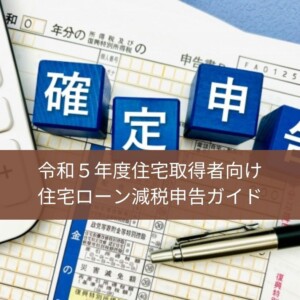不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」
前回では、「不動産取得税の対象となるもの」として、登記の有無を問わず不動産の購入・交換・贈与・建築などがありました。
(例外として相続による取得は非課税です。)
個人の住宅を取得した際には、土地・家屋ともに不動産取得税の軽減措置があります。
軽減措置の適用があれば、不動産取得税はゼロ~数万円程度ですむものもあるため、
今回はその軽減措置の具体的な要件などに触れたいと思います。
▼不動産取得税の計算方法
軽減措置の適用の前にまずは、不動産取得税の計算方法についてお伝えします。
不動産取得税は、課税標準額さえわかれば次の式により簡単に計算できます。
不動産取得税額=課税標準額×税率
不動産取得税を計算する場合の課税標準額は、市町村役場(東京23区は都税事務所)の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)によることが原則であり、実際の売買価格や建築工事費などではありません。
※また、贈与などによる取得の場合も贈与税における土地の評価方法とは異なります。
▼新築住宅における課税標準の特例(軽減措置)
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得(増築、改築を含む)した場合には、課税標準額から1,200万円が控除されます。
また、2020年3月31日までに取得する認定長期優良住宅では、この控除額が1,300万円に増額されることになっています。
家屋の不動産取得税額=(課税標準額-1,200万円)×3%
※ 一戸建て以外の貸家(マンション、アパートなど構造上独立した区画を有する住宅)の場合には40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
※ マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。
※ 住宅の用に供すること(自己の居住用または賃貸用の住宅であること)。
※ 1998年12月31日以前の取得では価格要件(1平方メートルあたり176,000円以下)がありましたが(新築、中古とも)、現在は価格による制限はありません。
※ 軽減措置の対象となる住宅を新築してから1年以内に、その住宅と一体になる住宅(離れなど)を別途新築したり、あるいは増築したりして合計床面積が240平方メートルを超えることになった場合には、その住宅全体が軽減措置の対象外として扱われ、当初の軽減分が追徴されることになります。
※ この場合の住宅(居住用家屋)の範囲には、いわゆるセカンドハウス(毎月1日以上など定期的に居住の用に供するもの)が含まれますが、別荘(保養目的で利用するものなど)は含まれません。
▼中古住宅における課税標準の特例(軽減措置)
以下の要件に該当する中古住宅を取得した場合には、課税標準額から一定額が控除されます。ただし、課税標準額のほうが控除額よりも低い金額の場合、不動産取得税額がゼロになるだけで還付などがあるわけではありません。
家屋の不動産取得税額=(課税標準額-控除額)×3%
【軽減措置を受けるための要件】
□ 個人が自己の居住用として取得したもの
□ 1982年(昭和57年)1月1日以後に新築されたもの(登記上の建築日付)
□ 1981年(昭和56年)12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの(「耐震基準適合証明書」など)
□ 1981年(昭和56年)12月31日以前に新築されたもので、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入したもの(2013年4月1日以降の取得にかぎる)
□ 家屋の取得後6か月以内に一定の手続きにより耐震改修工事を実施し、所定の証明を受けたもの(2014年4月1日以降の取得にかぎる)
□ 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
※ マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。
【控除額】
取得した中古住宅が新築された時期に応じて控除額が異なります。

▼住宅用土地における税額軽減の特例
以下の要件に該当する「住宅用土地」を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。
土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額
□ 新築住宅用の土地と住宅を同時に取得した場合
○ その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
○ 自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること
※ 宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を賃貸目的で取得した場合には、土地の軽減対象となりません。
□ 土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合
○ 1999年4月1日から2020年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内(本則は2年以内)に新築すること
※ 親が土地を取得し、子がその土地に住宅を新築するような場合にも適用されます。
□ 住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合
○ 軽減措置の対象となる住宅を新築した後、1年以内にその敷地を取得すること
○ 住宅を新築した者が土地を取得すること
□ 中古住宅用の土地を取得した場合
○ その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
○ 土地と住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後1年以内にその敷地を取得(当初は借地だったような場合)すること
○ 新築後1年を超えた未使用の住宅用土地(ただし、1998年4月1日以後の新築住宅の場合)を含む
○ 住宅取得者と土地取得者が同じであること
【軽減額】
次のうちいずれか「多いほうの金額」が軽減されます。
(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)a×b×3%
a=〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕
b=〔住宅の床面積×2〕
※ aの部分が〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕となるのは1996年1月1日から2021年3月31日までの取得であり、以降の取得では〔土地の1平方メートルあたりの価格〕となります。
※ bの部分は、1戸あたり200平方メートルが限度となります。
※ 住宅の持分を取得した場合は〔45,000円×持分〕または〔a×b×3%×持分〕です。
※ 土地の軽減額の計算に「住宅の床面積」が出てくるので勘違いしやすい部分です。間違えないように気をつけてください。
※ この軽減措置により、一般の住宅で土地面積が200平方メートル以下の場合には、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります。
不動産取得税は場合によっては高額になることもありますのでご相談ください。
以上、バイヤーズエージェント中田でした。