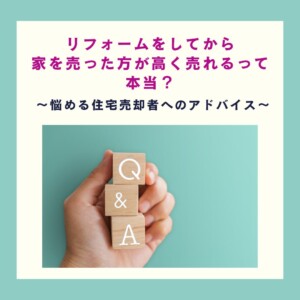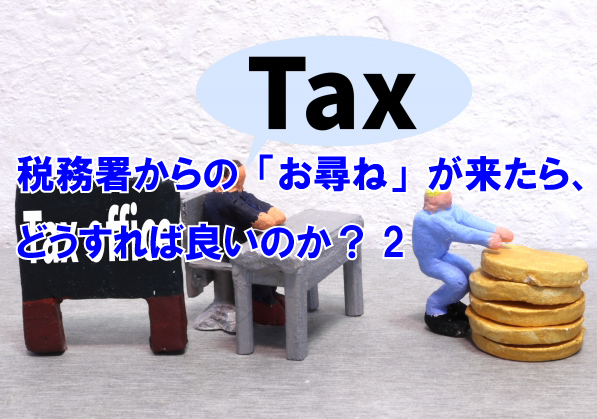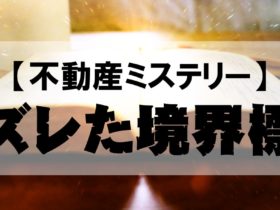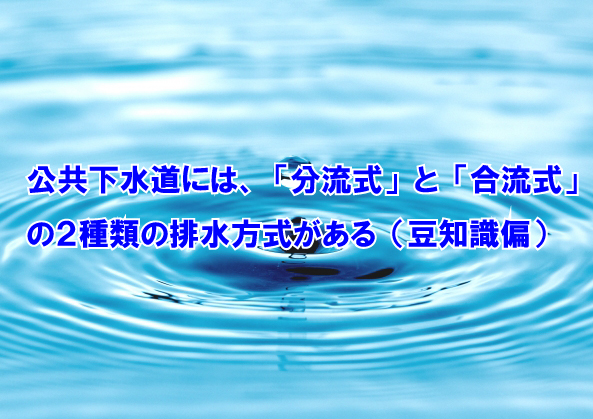2024年7月の日本銀行の追加利上げを受け、住宅ローンの変動金利が上昇し始めました。利上げ前に借りた人の金利は、多くの銀行で2025年から順次上がる計算となります。新たに借りる人向けの最優遇金利は、既に上がり始めていますが、継続的な顧客獲得のため、新規向け金利は足元でばらつきがあるのが現状です。金利が低い銀行や固定金利への借り換えなど、返済計画を工夫する好機でもあります。
■金利上昇で住宅ローンの総返済額を把握しておきましょう!
2025年1月の返済分から利息に充てる金額が約1万円増える家計は増えそうです。2024年6月以前に借りた方でネット系銀行を活用された方(5000万円、変動金利35年)は約0.35%前後の変動金利で借りている方が多いと思いますので、変動型の住宅ローン金利が来年1月から上がると適用金利は0.6%前後になる方が増えると思われます。勿論、金利が上れば返済総額は約数百万円単位で増加していきます。
住宅ローン金利には金利が一定の固定型と、半年ごとなど定期的に金利を見直す変動型があります。変動型の最優遇金利は長らく大手行で年0.3~0.4%台の水準が続いていました。住宅金融支援機構の直近の調査によると、新たに借りる人のうち約8割が変動型を選択しています。
■住宅ローンの「変動型」を選択している方へ
変動型は、日本銀行の政策金利の影響を受ける短期プライムレート(優良企業向けの1年未満の貸出金利)をベースに決まることが多く、金融政策の動向に左右されやすい金融商品です。各銀行は短期プライムレートなどに一定幅を上乗せし「基準金利」を決定しています。基準金利から収入や物件に応じた「優遇幅」を差し引き、「適用金利」を決めています。
2024年7月の日本銀行の追加利上げを受けて、多くの金融機関が基準金利を引き上げています。「金利のある世界」と題した記事も多く目にしました。借入中の人の適用金利は今後、年0.15~0.25%程度上がるケースが多く、以降も金利の動きに注目していきたいものです。
■金利上昇時には住宅ローンの「借り換え」を視野に!
金利上昇時の対応策の一つに借り換えがあります。別の金融機関で新たに住宅ローンを組み、返済中のローンを一括返済する方法です。借入中のローンよりも低金利のローンに借り換えれば、毎月の返済額や支払う利息を減らすことができます。変動金利での借り入れを固定金利に換えた場合には、毎月の返済額を確定させることもできる利点もあります。
■大手銀行も住宅ローンの金利にばらつきがある!
足元で新規の貸出金利はばらつきが見られ、三井住友銀行は11月の最優遇金利を年0.625%としましたが、三菱UFJ銀行、みずほ銀行は9、10月と同水準の年0.345%、年0.375%としました。従来、低水準の金利を提示してきた住信SBIネット銀行(年0.448%)、PayPay銀行(年0.465%)を下回る結果となっています。りそな銀行も他行に追随し、11月は年0.39%と前月比0.1%引き下げました。
多くの場合、借換時の金利は新規向けと同じ金利を適用しています。金融機関の金利差がある状況では、借り換えで返済額を抑えられる可能性は高まると言われます。より低い変動型への借り換えを勧めるケースもありますが、残存期間にもよりますが、利上げ後の適用金利0.7%前後(利上げ前0.5%台半ば)が借り換えで得するかの目安となります。
例えば変動型で年0.7%から0.4%に借り換えるケースだと、手数料を含めた試算によると、返済期間が残り30年、残るローンの金額(残債)が3000万円では、毎月返済額が約1200円減り、返済総額では約40万円減らせます。基準金利から差し引く優遇幅は完済まで一定のため、2つの銀行が同じペースで基準金利を動かすなら、低い金利に借り換えた恩恵は返済終了まで続きます。残りの返済期間が長く、残債が多いほど恩恵は大きいと言われますが、元々変動金利を選択しているので、今後の情勢を見ての再見直しが必要となります。
一般に借り換えには諸費用がかかり、新たな金融機関で諸費用分も借りる場合が多いです。新たに借りる際に借入額の2.2%などが必要となるほか、元の銀行への一括返済にも手数料がかかります。返済期間が短い場合や残債が少ないと、諸費用分の借入額の増加で、低い金利に換えても、返済額が増えることがあります。検討する時は、諸費用を含めて試算する必要があるので注意が必要です。もっとも、変動型から変動型に借り換えても金利上昇のリスクは残る事はお忘れなく。目先の損得よりも、見通しの安定性を重視するなら、固定金利への借り換えが一案となります。
■住宅ローンを「変動型」から「固定型」に変える場合
固定型の代表格「フラット35」の金利水準は足元で年1.8~1.9%台となっています。SBI新生銀行の借り換え向けの35年固定金利は年1.55%と、変動型と差があります。しかし、固定型は変動型と比べれば高くみえますが、歴史的にみれば低水準となります。金融機関によっては変動型との金利差が縮小している商品もあり、今は狙い目となります。固定型に換えれば、毎月の返済負担は増えますが、完済まで返済額が確定する点がメリットとなります。
例えば年0.7%の変動型から年1.8%の固定型に借り換えると、返済期間が残り30年、残債3000万円なら、毎月返済額は2万円弱増えます。変動型の金利が一定なら、総返済額で700万円近い増加となりますが、金利が上昇すれば、固定型の返済額を上回ることもあります。負担額が増えるデメリットはありますが、計画的な家計運営ができる点はメリットとなります。変動型のまま物価と住宅費の両面で上昇リスクを抱えるより、老後資金などを確保しやすいです。
一般的に変動型の返済額が固定型を上回るケースは金利が2%程度上昇した場合と言われています。固定型で借りる金額を2~3割にとどめ、借り換えによる返済額の増加幅を抑える方法もあります。貯蓄額や資金計画を考え、家計に合った対応策を考えていただければ幸いです。
以上、金利上昇局面での「住宅ローン」の選び方について解説をしてきましたが、最終的に住宅ローンを組まれる方の判断に委ねられます。今後の参考にお役立ていただければ幸いです。