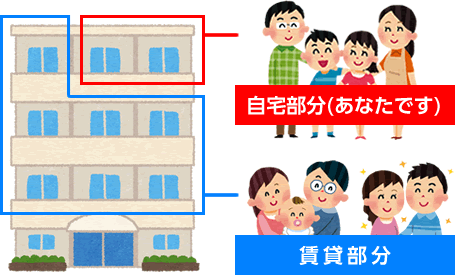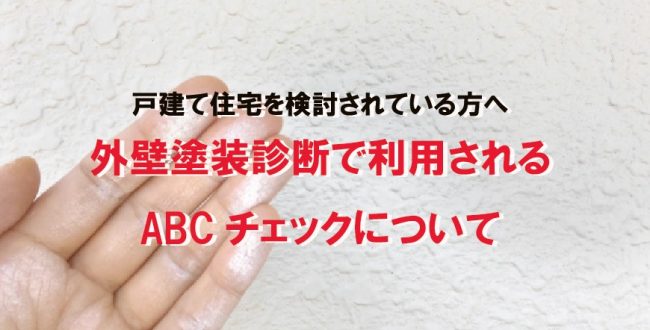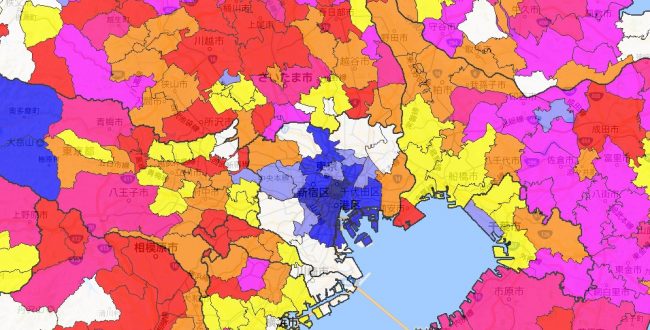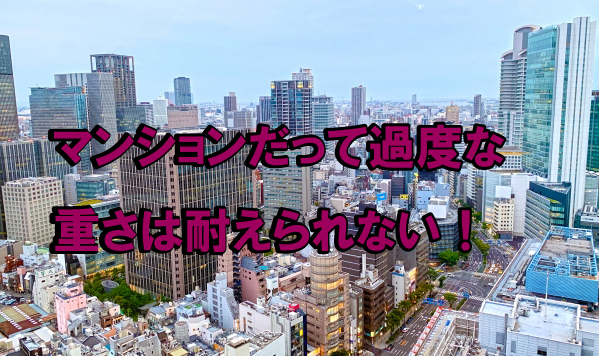年末年始を実家過ごす方も多いかと思います。その際に実感される方も多いかと思いますが、子供の時には大きく感じた親の存在も、帰省で接した親の姿は小さく見えるというものです。その際に介護施設への入居を本格的に検討し始めるといった人もいると思います。「終(つい)のすみか」を移すのに費用がかかるのは当然となりますが、税金面での検討も必要となります。夫婦や親子の間で曖昧にしていた現実に向き合うタイミングになるかもしれません。その為、今回は老人ホームの入居と税金について解説をしたいと思います。
■「居住用不動産」に該当しない老人ホームは贈与の仕方を検討する!
有料老人ホームの料金は「前払い金(入居一時金含む)」と、毎月発生する「月額費用」の2本建てとなります。最近は「前払い金無し」の施設も増えているようですが、前払い金の相場は数十万〜数千万円と幅があります。勿論、前払い金が多ければ、相対的に月額費用の出費は抑えられる傾向があります。しかし、夫婦の一方が他方の入居費用を支払う場合、贈与税などの税負担が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
夫婦間では生活費に充てるために通常必要と認められる範囲での資金融通は贈与税の対象外となりますが、過去には多額の入居費用の支払いを巡り課税されたケースもあります。
婚姻期間20年以上の夫婦には、居住用不動産や居住用不動産の取得費用の贈与は2000万円まで課税されない特例もありますが、老人ホームは「居住用不動産」に該当しませんので、この課税される可能性が高いものとなります。契約形態にもよりますが、前払い金が高額な施設への入居を検討する場合は特に、夫婦それぞれの資金を区分したうえで費用を準備しておく工夫が大切です。贈られる側1人につき年110万円まで課税されない暦年贈与の制度は一つの選択肢になります。
■想定居住期間内に退去した場合、実際の居住期間に応じて一部が返還される?!
前払い金は退去時に返還される場合があり、詳細は契約書類をご確認ください。前払い金は施設側が平均余命などを基に設定した「想定居住期間」の家賃に充てられ、相対的に月額費用を抑える効果があります。前払い金の一部を想定居住期間後の家賃に充当するため「初期償却」する施設もありますが、想定居住期間内に退去した場合、実際の居住期間に応じて一部が返還されるといったものです。
契約時に返還分の受取人を決めることになるが、入居者本人が前払い金を支払っていて相続が発生した場合、返還分は相続財産となるので、遺産分割や相続税の申告時には忘れないようにしてください。
■老人ホームへの入居後、「空き家」には場合は注意が必要!
老人ホームへの入居で実家が空き家になるケースもあると思います。いずれは必ず発生する相続を見据え、自宅の土地330平方メートルまで評価額が8割軽減される「小規模宅地等の特例」の適用条件がある事をご存知でしょうか?
老人ホームに入居後の自宅が相続税制上の「自宅」として扱われるには、持ち主が要介護や要支援の認定を受けている必要があります。自立した生活を送れる段階で入居できる「入居時自立型」の施設もありますが、相続時点で認定を受けていれば問題はありません。
しかし大前提として、老人福祉法などで規定する施設でなければ適用除外となります。厚生労働省の調査によると、2023年6月末時点で未届けの有料老人ホームは全国で604件ありますので、注意が必要です。
自宅で暮らしていた持ち主が老人ホームに入居した後も、同居親族が住み続けていれば特例の対象になりますが、生計を別にしていた親族が空き家に移り住んできたケースは特例が認められません。将来実家に住む予定があれば、税制面では「親の一人暮らし」は同居を検討する該当するケースもあるようです。配偶者が相続する場合は、仮に同居していなくても特例は適用となります。
実家の不動産が最も高価な相続財産というケースが多く、相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除を超えた分に課税されます。特例が適用されず、現金や有価証券といった換金性の高い財産が乏しいと、相続税のために実家を売却する必要も出てきます。
空き家状態で相続が発生しても一定の条件で売却した場合は「空き家特例」があり、マンションは対象外となりますが、相続後に売却して得た収入について、建築時期や売却時期、売却代金といった要件を満たせば、3000万円まで課税対象から控除されます。
空き家を放置して管理状態が悪いと自治体が「特定空き家」に指定して、固定資産税の大幅な引き上げや行政代執行による家屋の取り壊し費用の請求対象にもなるので注意が必要となります。
いずれにせよ、これから「空き家問題」「老人ホームへの手続き」等の親の対応が必要となる方も多いかと思います。
今後の参考にお役立てください。
法人営業部 犬木 裕