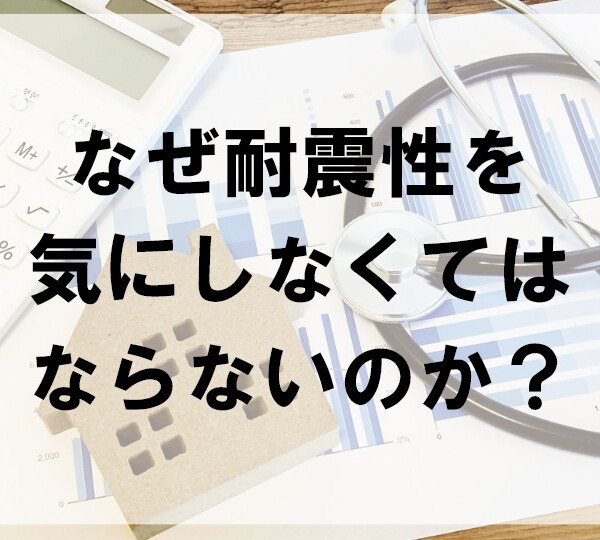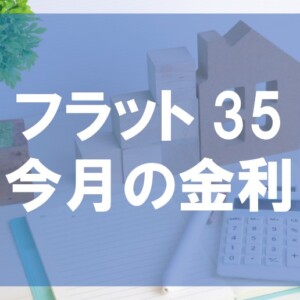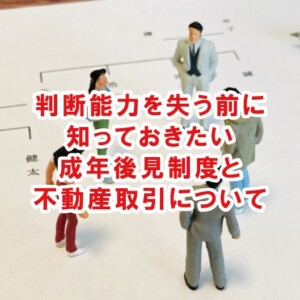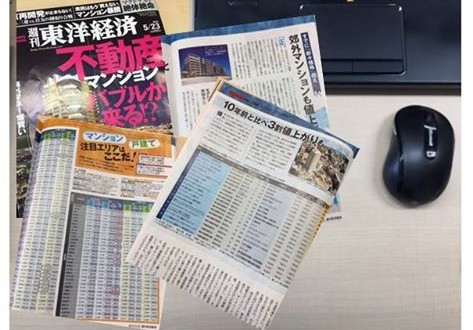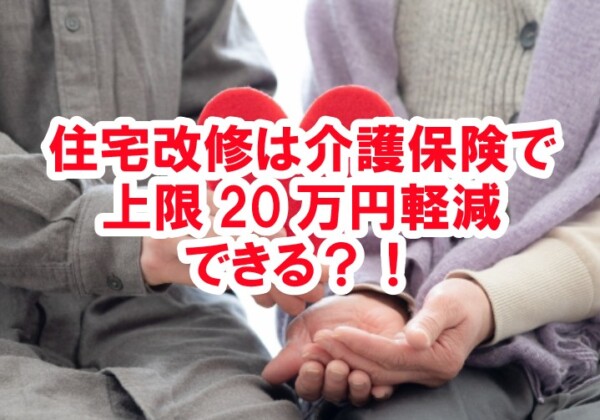大きな地震被害などが起きると住宅の耐震性が話題になります。
住宅購入の場合、中古住宅検討時には耐震性は重要な検討材料の一つです。
しかし一般に流通している物件でなぜ耐震性を気にしなければならないのか疑問に思う方も多いと思います。
今回は住宅の耐震性についてご説明いたします。
■耐震性に問題のある物件を取引してはならないという法律はありません
不動産取引において、住宅の耐震性について何らかの法律の制限があるとお考えの方は多いです。
しかし中古住宅の場合、不動産売買契約における重要事項説明書の中に、耐震診断書の有無をチェックする欄があり、有の場合にはその内容を説明しなければならない、とだけが規定されていて、例えば取引にあたって耐震診断を実施しなければならない、といった法律の制限はありません。
つまり言い換えると、住宅の耐震性は買主側の責任で対策を講じなければならないということになります。
これが新築の場合は異なります。
新築は建築した事業者が10年間保証をしなければならないという法律になっていて、あくまで建築基準法の範囲内ですが、建物に瑕疵がある場合は、建築した事業者の責任が問われます。
言い換えると、新築の場合は、耐震性が確保された住宅しか流通していない(但し欠陥住宅は除く)と言うことになります。
■建築基準法を過信しない
日本では住宅の建築に当たって建築基準法の制限を受けます。
建築基準法には耐震性に関する項目も存在することから、建築基準法をクリアした住宅なら一定の耐震性能を確保していると判断されます。
ここで多くの方が誤解しているのが、建築基準法は最低基準でしかない、ということです。
住宅性能表示制度における耐震等級がわかりやすいので例にしますが、耐震等級は1~3までランクがあって、数字が大きければ大きいほど高い性能を有していることとなります。
耐震等級1が建築基準法と同等と位置付けられます。
耐震等級2は建築基準法レベルの1.25倍、耐震等級3は1.5倍と位置付けられています。
耐震等級3の住宅なら安心だ、という表現はおかしくないのですが、「この家は建築基準法をクリアしているから安心だ」というのは少しおかしな判断と言えます。
この建築基準法は最低基準でしかないという考え方は非常に重要なのでぜひ正しくご認識ください。
■いつの建築基準法ですか?
もう一点、建築基準法について注意があります。
建築基準法は改正を繰り返している、ということです。耐震については、大きな地震被害が発生するたびに改正されています。
住宅を建築する際には建築基準法に定める通り設計・建築されているかを確認するプロセスがありますが、建築基準法改正前の基準をクリアしていても、改正後では基準を満たさないことはよくあります。
従って中古住宅を購入する際のチェックポイントは、いつ建てられた住宅なのか?ということになります。
最も影響が大きなタイミングは1981年6月の改正です。
建物の強さに直結する壁の強さに関する規定が改正され、その影響も大きなことから、1981年5月以前の建物を「旧耐震」と呼び、既存不適格住宅と位置付け、耐震の対策が必要な住宅という認識となっています。
1981年6月以降の「新耐震」なら大丈夫かというとそうでもなく、阪神淡路大震災の教訓を受け、2000年6月に建築基準法が改正されており、新耐震であっても2000年5月までの建物は耐震診断や改修工事を行った方が良いとされています。
建築年月は不動産広告でも目立つ位置に記載されていますが、築年数から建物の古さをイメージするのが目的ではなく、どのタイミングの建築基準なのかを判断する重要な情報と言えます。
■自己責任に陥らないために
新築のように耐震性を確保しなければ取引できない仕組みであれば良いのですが、残念ながら中古住宅取引にはそのような制限はありません。
中古住宅売買で「耐震性が重要です」というような情報が多いのは、結局のところ買主の自己責任になってしまうからです。
とは言え住宅購入時にはいろんなことを同時に検討しなければならないため、耐震性ばかり注目する訳にはいきません。
そこでお勧めなのが中古住宅を安心して購入するために国が用意した制度を利用することです。
国の制度を利用するには多くの場合建築士に頼まなくてはならないので、耐震性が軽視されるという結果を避ける可能性が高くなります。
また、不動産仲介会社も中古住宅を取り扱う以上、住宅の耐震性について詳しい会社もあります。
取引の初期段階で積極的に疑問をぶつけて、十分な知識やスキルを持っているかを確認することも重要な確認作業と言えます。
住宅の耐震性は、中古住宅の購入時には欠かせない重要な検討材料です。
買主の自己責任で判断するのは荷が重いので、取引に携わる仲介会社を通じて、建築のプロである建築士に相談するのがお勧めです。