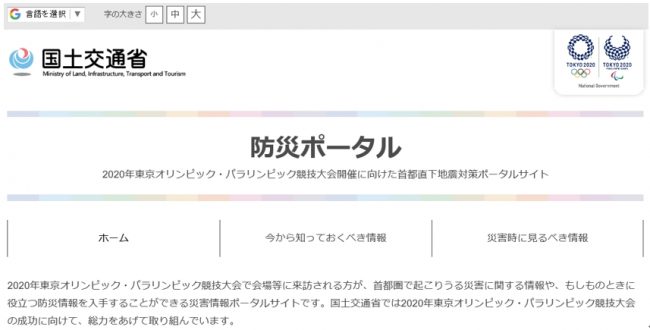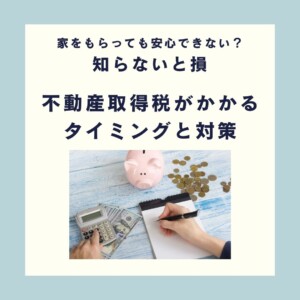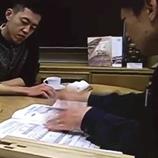災害発生時に避難所に避難する、という従来型の避難戦略は、避難所設置余地の少ない都市部への人口集中や避難の難しい高齢者の増加、感染症対策のための安全距離の確保による避難所収容力の低下などを背景に、限界を示しつつあります。
この課題へのソリューションとして注目されているのが、自宅に留まり安全に避難する“Shelter in place”という米国の考え方です。日本でも、避難所まで移動する「水平避難」に対して、その場に留まる「待避」や建物の上層階に登る「垂直避難」を状況に応じて使い分ける考え方が一般化しつつありますが、”Shelter in place”はさらに一歩進んで、自宅避難を想定してあらかじめ災害に強い家を作り、災害時の自宅避難の可能性を能動的に高めていく動きです。
今回はShelter in placeという概念を取り入れた新しい災害時避難の枠組みを「避難所2.0」と呼び、それを推進する動きとして、立地選択や建物建築に対するインセンティブの強化、中でも重要な取組みとして、災害に強い家に「認証」を与える方向性について考察します。
新しい避難の枠組み実現のための要件
先に触れた新しい避難の枠組み、「避難所2.0」を実現するためには、制度面を整備することにとどまらず、人々の意識を変え、行動変容を起こすためのソフト面からのアプローチが重要になってきます。
災害発生前には「人々が災害に強い家を建てること(立地・構造要件)」が、災害発生時には、「状況に応じて最適な避難行動をとること(最適行動選択要件)」が求められます。
建物の構造・立地要件としては、災害リスクの低い土地に家を建て、災害が発生してもそれに耐える構造の家を建てることが求められます。しかし、過去に被災した土地や災害への備えが弱い家は、初期の購入コストが低いため、災害に弱い土地に災害に弱い家を建てることにメリットが生じてしまいます。
これを修正するためには、行政等が意図的に介入することも必要となります。例えば、国土交通省では、2021年5月の改正法公布を受け、「長期優良認定制度の見直しに関する検討会」を設置し、災害配慮の考えを含む長期優良認定制度の新基準について議論を重ねました。これにより、2022年2月より認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が追加され、災害の危険性が時に高い区域を認定対象から除外し、災害リスクが高い区域では、必要な措置を求めることができるようになりました。
【長期優良認定制度における災害配慮の基準】
○認定を行わないことを基本とする区域の例
- 土砂災害特別警戒区域
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
○認定を行わない、または、認定に当たり必要な措置を求めることができる区域の例
- 浸水被害防止区域
- 災害危険区域
- 津波災害特別警戒区域
○認定に当たり必要な措置を求めることができる区域の例
- 津波災害警戒区域
- 土砂災害警戒区域
- 洪水浸水想定区域
- 雨水出水浸水想定区域
- 高潮浸水想定区域
また、行政が今後このような「避難所2.0」の考え方をとりいれ、人々に対して、災害時には避難所への移動だけでなく自宅に留まる選択肢もありうるという立場を強調するようになれば、逆に、どんな災害が起こってもどんな家に住んでいても、自宅に留まろうとする傾向がこれまでよりさらに強まるでしょう。
そのため、「避難所2.0」の時代における災害時リスクコミュニケーションは、従来同様あるいはそれ以上に、自宅に留まっては危険な人に対して「避難所に避難してください」というメッセージを伝えることが重要になるものと考えられます。それによって、垂直避難と水平避難を有効に使い分ける「最適行動選択要件」が満たされることになるでしょう。
これら「避難所2.0」の取組みにより、安全な場所に安全な構造の家が数多く建つことにより地域全体の防災力が底上げされ、公的な防災コストの削減につながると考えられます。さらに、災害時には安全な家に住む人々に的確に自宅待機を選択してもらうことで、避難所のキャパシティや維持コストをコントロールしつつ、自宅に留まった人々・避難所に移動した人々、双方の被災者のQOL(生活の質)を高めていくことが可能となります。
まずは、災害に弱いエリア・住宅の選択をしないよう、住宅購入時には確認が必要となるかと思いますので、ご自身での確認も勿論ですが、その辺りも助言してくれるエージェントを探す方がより安全な住宅選びにつながるかと思います。
リニュアル仲介の前田でした。