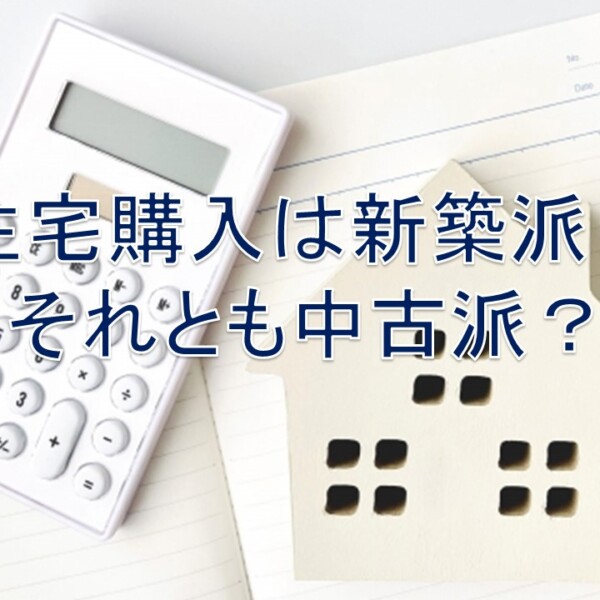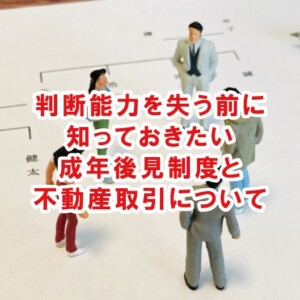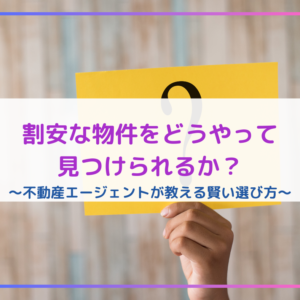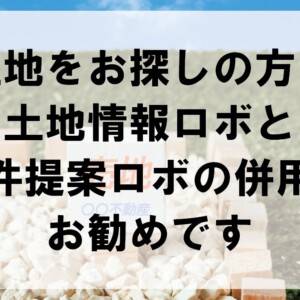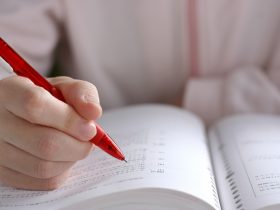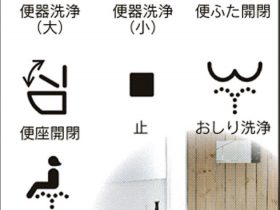欧米では、住宅流通に占める中古住宅の割合が約8割といわれています。
一方、日本でも近年、新築住宅の価格高騰や供給数の減少などを背景に、中古住宅の流通量が増加しています。
中古住宅が選ばれる理由はさまざまですが、第一の要因はやはり「価格」です。
新築住宅の価格は、資材費や外注費の上昇を受けて、ここ数年で1〜2割ほど上昇しています。
さらに実質賃金の伸び悩みや住宅ローン金利の上昇もあり、高額なローンを避ける傾向が強まっています。
このような市況の中で、経済的負担を軽くしたいという購入検討者が増えているのは自然な流れです。
また、中古住宅でもリフォームやリノベーションによって快適で魅力的な空間を実現できることが広く知られるようになりました。
断熱性能や耐震性能も改修によって向上させることが可能で、「性能面でも新築並み」にできることが、中古住宅の人気を押し上げています。
■中古シフトが加速している理由
中古住宅の流通比率は年々上昇しており、2022年には「42.3%」と過去最高を更新。
直近10年間で約10ポイントも増加しています。
この「中古シフト」が進む背景には、次のような要因があります。
・新築住宅の価格高騰
不動産経済研究所によると、首都圏の新築マンション平均価格は2014年の5,060万円から、2024年には7,820万円へと上昇。
戸建住宅も、建材や人件費の高騰により価格上昇が続いています。
・新築住宅の供給数減少
2000年前後には首都圏で年間10万戸近くの新築マンションが供給されていましたが、2024年には約2万戸強にまで減少。
高価格・低供給となった新築住宅は、いまや「高嶺の花」となっています。
・社会構造の変化
空き家の増加や少子高齢化の進行により、中古シフトは自然な流れともいえます。
都市部では引き続き人口増加が見込まれていますが、住宅用地は限られています。
再開発や建て替えは進むものの、新築住宅の供給数は限定的です。
■中古住宅の魅力
中古住宅には、新築住宅にはない魅力があります。
・価格が安い
・物件の選択肢が多い
・実際の建物を見てから購入できる
■中古住宅を購入するときの注意点
中古住宅は魅力が多い一方で、耐震性能や経年劣化などのリスクにも注意が必要です。
購入時には、次の点をしっかり確認しましょう。
・築年数ごとの耐震基準を理解する
耐震基準は、建築確認申請の時期によって異なります。
区分 主な内容 適用開始
旧耐震基準 震度5強程度で損傷しない 1981年5月以前
新耐震基準 震度6強〜7でも倒壊しない 1981年6月〜
2000年基準(木造のみ) 木造住宅の基礎・接合部などを明確化 2000年6月〜
築年数だけで耐震性を判断するのは危険です。
旧耐震基準の建物でも耐震補強により安全性を高めている場合があります。
また、メンテナンス状況によっても性能は大きく異なります。
・建物のコンディションを確認する
同じ築年数でも、住まい方や管理状況によって建物の状態は大きく違います。
そのため、第三者の専門家による「インスペクション(建物状況調査)」を活用するのが有効です。
国もこの制度の利用を推進しており、安心して中古住宅を選ぶための重要な手段となっています。
・リフォーム・メンテナンス費を見込む
中古住宅の平均築年数は上昇しており、首都圏では20年を超える物件も一般的です。
購入者の半数以上が、購入後に何らかのリフォーム・リノベーションを実施しています。
購入時には、将来的な修繕やメンテナンス費用も含めて資金計画を立てることが大切です。
■まとめ
今後も中古住宅の流通は拡大し、「中古を買ってリフォームする」という選択肢がより一般的になっていくでしょう。
リフォーム・リノベーション・インスペクションなどの関連市場も成長しています。
近い将来、「家を買う=中古住宅を買う」という時代が来るかもしれません。
購入の際は、見た目だけでなく建物の「コンディション」をよく確認し、豊富な選択肢の中から自分たちに最適な住まいを見つけていきましょう。
リニュアル仲介、渡辺でした。