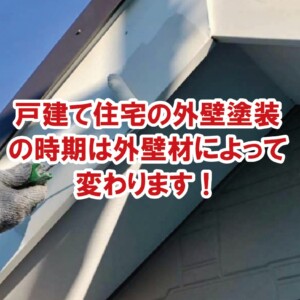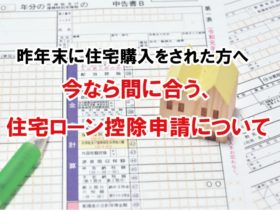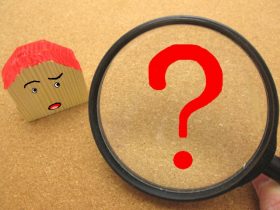熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
私の父方・母方、両方とも熊本市内に実家があり、多くの親せきが被災しております。
阪神淡路大震災をきっかけに住宅の耐震化に携わることになった私が今できることとして、少しの知見ではありますが、過去の災害ボランティア活動からの経験で情報を発信します。少しでも何かお役に立てればと思います。
早く元の生活に戻りたい一心で、家の修繕を始められる方もいらっしゃいます。しかし、り災証明・損害認定などが無いと「公的支援が受けられない」「損害保険が支払われない」という事態が発生します。手を加えられる場合には、なるべく写真・動画などで正確に証拠を残しておく必要があります。
以下、被災住宅の手続きの順番でお伝えします。まずは、応急危険度判定、り災証明書の申請を最寄りの自治体にされることをお勧めいたします。(混乱していて、受付対応が十分でなかったり、調査がずいぶん先になることも予想されます。)地震保険に加入されている方は、保険会社に保険金払い出しの請求をされることをお勧めします。
①緊急判断
緊急性が高いこととして、そもそも荷物を取りに行ったり、片づけに家に入ってよいかということです。相次ぐ余震で倒壊するかもしれません。この判断は、建築士がいればお願いし、少しでも建築に携わったことのある人に意見を求めることです。これは、公的な立場・手法ではありませんが、緊急性が高い場合はやむをえません。折れている柱が1本でもあった場合、既に垂直荷重を受けられていないので、住家に入ることはやめた方が良いでしょう。この段階は、平成28年4月23日現在、もう過ぎているように思います。
②応急危険度判定(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/oq/index.html)
公的な危険度判定です。判定士の資格を持った建築士が全国から集まり、自治体を通じて「調査済み」「要注意」「危険」の3種の判定をします。本来は急いで行う必要があるものですが、人命救助、最低限のライフラインの確保、避難所の整備等のほうが緊急性が高いため、少し落ち着いてから順次行われます。避難所生活の皆様は早く家に帰りたいところですが、判定を受けてからが安心だと思います。
参考:熊本県の被災建築物応急危険度判定窓口 土木部 建築課 TEL:096-333-2533
③り災証明書
自治体による被害認定です。「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4種の判定をします。「被災者生活再建支援金」の支払いを受けられることもあります。この支援金を受けるにあたり、必要となる書類が「り災証明書」で、これは住居の被災の程度を示す書類です。
参考:熊本市のり災証明について
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2451
災害に関わる住家の被害認定基準運用方針
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/shishinall.pdf
④損害保険会社の損害認定
被保険者からの請求に応じて、専門の判定員が派遣され損害認定を行います。損害保険会社は全国から判定員となる建築士を募集して派遣するので、多少時間がかかると思います。損害保険会社による損害認定と自治体による被害認定の内容は同じではありません。両者の認定基準が異なるため、損害保険会社で半損と認定された損害でも、自治体による認定では全壊と認定されることがありえます。
⑤耐震診断
今までのものは、危険性の判定や被災状況の認定であり、構造的にどうであるかを見るものではありません。危険性の判定、被災状況の認定の手続きを経てから、耐震性の確認という流れになると思います。被害住宅の修繕と耐震性の確保、ついでにリフォームなどを検討することになります。耐震診断や改修については補助金が出る場合があります。しかし、戸数限定であったり(熊本市の耐震診断費用助成は平成28年度分は2戸)、平成28年4月23日現在は、年度替わりのタイミングでもあるので、執行が5月に入ってから(熊本市の耐震改修費用の補助は平成28年5月6日から)だったりします。ほとんどの自治体は、申請後に耐震診断の申し込み、耐震改修工事の請負契約をしなければならないので、注意が必要です。詳しくは、最寄りの自治体にお問い合わせください。
参考:熊本市耐震診断費用助成
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1330
熊本市戸建木造住宅耐震改修事業
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1284&class_set_id=3&class_id=633