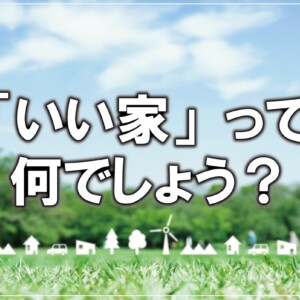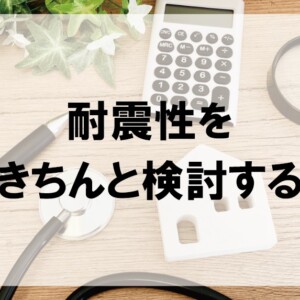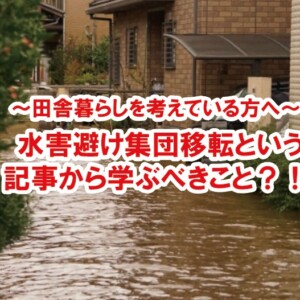コロナ禍において提唱される人と人とのソーシャル・ディスタンスですが、同じように不動産についても、防災の観点から建物間の適正な距離の確保が求められます。
その指針を示している法律が、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」
いわゆる「密集法」です。
密集市街地とは?
密集法に定める「密集市街地」とは、老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、公園や空地などの十分な公共施設が整備されていないこと等から、防災機能が確保されていない市街地のことを指します。
単に建物が密集しているというだけではなく、建物自体が老朽化していたり、火事又は地震が発生した場合の延焼の防止や避難の際に確保されるべき機能が満たされていない市街地を指します。
元々は、阪神大震災の際の教訓を活かし、大規模な地震が発生した際の被害の拡大を抑えることを目的として制定された法律です。
密集市街地を解消するための再開発計画
密集法では、密集市街地を解消するために「防災再開発促進地区」を定めることができるとされています。
これは、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべきとされた一定規模以上の地区について、整備又は開発の計画を定めながら密集市街地の解消を行う、というものになります。
この中では、建物と建物の距離の確保や、公園などの空き地の整備、消防車両がスムーズに侵入できる道路の確保、建物の防火措置などを一体的に定めていくことで、街全体の防災機能の向上を達成していきます。
防災再開発促進地区にある老朽化建物
このように、大きな計画のなかで街の防災機能を高めていく密集市街地の解消ですが、一方である程度強制的に開発を促進していく側面もあります。
例えば、この地区内にある老朽化建物については、一定の条件に基づき行政庁から建物解体の勧告をすることもできるとされています。
現在は、空地・空き家なども大きな話題となっており、老朽化建物の存在が近隣への迷惑となっているケースもあります。
災害時のリスクという面からも、老朽化建物については解体勧告の措置が必要との判断になります。
お住まい探しをする場合には、人口動態などから街の成長力を測ることも大切ですが、併せて都市計画や再開発計画など、街の活性・防災事業計画の面からの検討も大切です。
震災に対する対策が図られている街かどうかは、お住まい探しの大きな要素になるのではいでしょうか。